湊御殿の建築
丸桟瓦(まるさんがわら)

これは、解体前の本建物に葺かれていた瓦です。丸瓦(まるがわら)と平瓦(ひらがわら)を合わせて一体に作った「桟瓦(さんがわら)」で、特に屈曲が大きく丸みを帯びているので「丸桟瓦」と呼ばれています。なかには「泉州貝塚」や「泉貝瓦治」の刻印を持つ瓦が一定量ふくまれており、それらは江戸時代に大阪南部の貝塚寺内町(かいづかじないまち)で焼かれたものです。

湊御殿は文化12年(1815)に焼失した後、十一代藩主斉順(なりゆき)治世の天保5年(1834)に再建され、明治時代初期に和歌浦に移築されます。再建後の修理の際にも新しい瓦が補充されますが、御殿内展示の瓦は天保期の再建時のものと考えられる資料です。 丸桟瓦は和歌山独特の瓦で、和歌山城内の御橋廊下や市内禰宜所在の重要文化財旧中筋家住宅の主屋などにも葺かれています。
広間(ひろま)
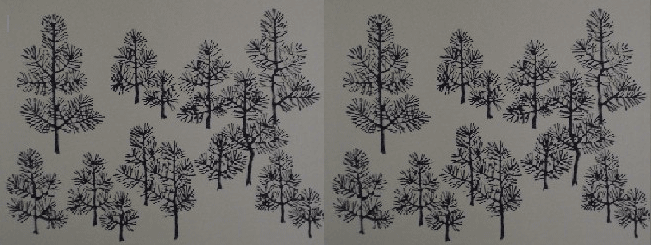
襖(唐紙)には胡粉(ごふん)による「綾菱地(あやびしじ)」の地文様に、縹藍(はなだあい)で「若松」を配しています。

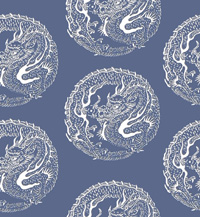
天井(唐紙)には縹藍の地に胡粉で「龍の丸」を配しています。

釘隠し。
杉戸絵(すぎとえ)

表面「唐人人物画(とうじんじんぶつが)」。紀州藩御抱絵師による作品といわれています。杉戸絵は建物の風格を表しています。

裏面「花鳥図」。

杉戸の引き手金具には、宝相華唐草文(ほうそうげからくさもん)の意匠が彫られています。
書院造り(しょいんづくり)

書院造りとは、部屋に床や棚を設けた様式をいいます。違い棚(ちがいだな)や棚の上部にある天袋の小襖の引き手金具などには「葵紋」の金具が取り付けられおり、紀州徳川家の建物であったことがわかります。

飾り金具は、魚子(ななこ)を打った赤銅地に徳川家の家紋である「葵紋」と唐草文に鍍金(めっき)を施した金と黒のコントラストが豪華なものとなっています。
